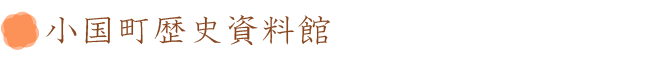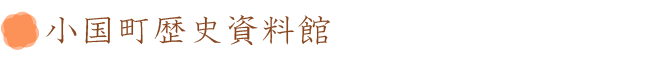
●現代(戦後~)
戦争が終わり、次第に現在の小国の姿へと変わっていきます。
| 1948 |
昭和23年 |
柏崎農業高等学校小国分校を誘致。43年全日制になり、49年柏崎高等学校小国分校となる |
| 1956 |
昭和31年 |
小国町誕生 |
| 1958 |
昭和33年 |
東京小国会創立 |
| 1967 |
昭和42年 |
小国中学校創立 |
| 1976 |
昭和51年 |
小国町就業改善センター開設。「小国町史」発刊 |
| 1979 |
昭和54年 |
延命寺ヶ原森林公園開園 |
| 1981 |
昭和56年 |
56豪雪 最高積雪342センチ |
| 1982 |
昭和57年 |
小国町役場新庁舎完成 |
| 1984 |
昭和59年 |
59豪雪最高積雪346センチ |
| 1986 |
昭和61年 |
国道291号線武石トンネル開通 |
| 1988 |
昭和63年 |
小国町農協と上小国農協合併「小国農協」スタート |
| 1988 |
昭和63年 |
第1回おぐに雪祭り開催 |
| 1990 |
平成2年 |
民俗資料館開館 |
| 1992 |
平成4年 |
小国芸術村友の会地域活性化大賞受賞 |
| 1993 |
平成5年 |
クリーンセンター完工 |
| 1996 |
平成8年 |
自然休養体験施設「養楽館」オープン |
| 2001 |
平成13年 |
新桜町トンネル供用開始 |
| 2002 |
平成14年 |
第1回もちひとまつり |
| 2004 |
平成16年 |
長岡合併協定調印 |
| 2004 |
平成16年 |
新潟県中越地震発生 震度6強2回 |
| 2005 |
平成17年 |
長岡市に編入合併 |
| 2006 |
平成18年 |
大貝トンネル完成 白倉大橋供用開始 |
| 2007 |
平成19年 |
中越沖地震発生 |
■行政区の移り変わり
明治の初め、新潟県は、新潟県と柏崎県に分かれ、小国は柏崎県に属していました。当時は現在の各集落がそれぞれ村を構成していました(大字太郎丸が太郎丸村、大字新町が新町村…というように)。明治22年に市町村制が施行され、町村合併で千谷沢村、中里村、増田村、結城野村、森山村、法末村、武石村、七日町村、横沢村、山横沢村の10の村ができました。このうちの4つの村が合併して明治34年上小国村が生まれました。その後、合併を繰り返し、昭和31年に小国町となりました。平成17年4月1日には、中之島町、越路町、三島町、山古志村とともに小国町は長岡市に合併し、「長岡市小国町」となりました。
|
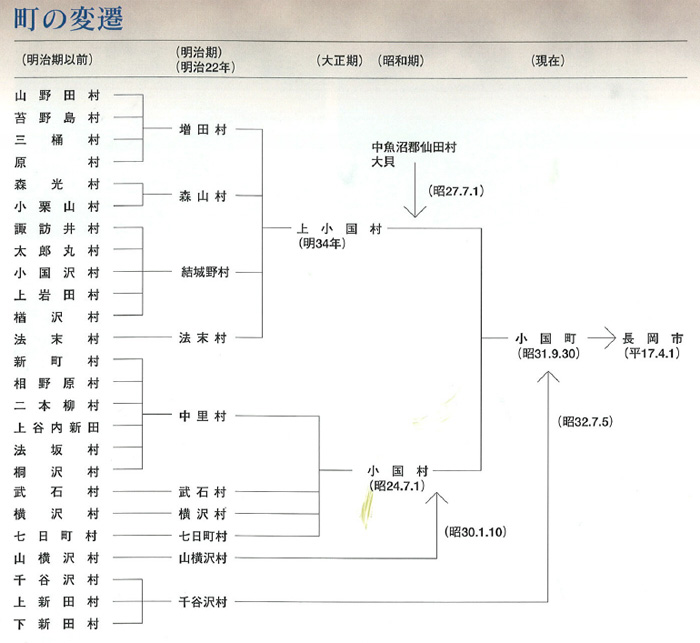
町の変遷(図をクリックすると拡大します) |
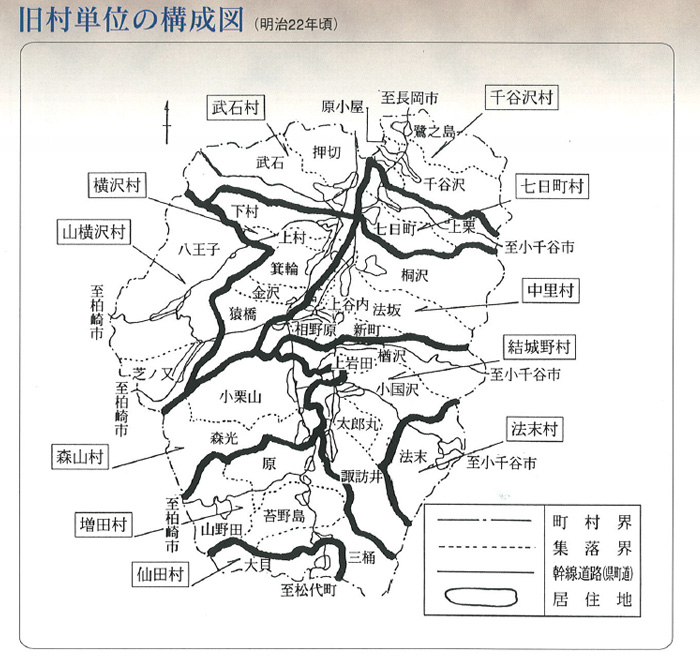
旧村単位の構成図(図をクリックすると拡大します)
|
■学校

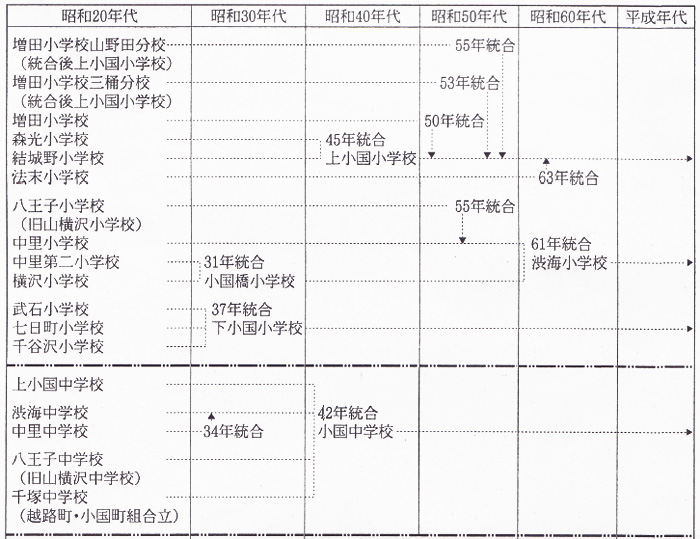
小国郷内各学校の変遷
(図をクリックすると拡大します)
|
江戸時代、小国には各地に寺子屋があり、子どもたちは習字などを習っていました。明治5年、学制が発布されて尋常小学校ができました。昭和16年になると国民学校と名前が変わり、昭和22年に今と同じく小学校6年と中学校3年が義務教育になりました。
明治の学制施行の頃、小国には太郎丸校や原校とよばれる学校がありましたが、やがて次の小学校になりました。
結城野小学校、法末小学校、森光小学校、増田小学校(三樋分校・山野田分校)、中里第一小学校、中里第二小学校、七日町小学校、武石小学校、横沢小学校、山横沢小学校(菅沼分校)。
子どもの数が減少するにつれて次々と統合を繰り返し、現在は上小国小学校、渋海小学校、下小国小学校と、三校になっています。
中学校は昭和22年の学制では上小国中学校、中小国中学校、中里中学校、渋海中学校、千塚中学校の5つでしたが、現在は小国中学校1校となりました。 |